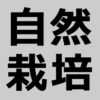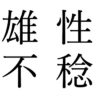自然栽培の甘夏(あまなつ)を購入しました。
柑橘類ってたくさん種類がありますよね。夏みかん、いよかん、はっさく、甘夏・・・、わたしは柑橘類の見分けがあまり良くわかりませんが、わたしだけではないと思います。柑橘類の見分け方って、わからない人の方が多い気がします。
甘夏(あまなつ)ってどんな果物なの?
甘夏の元となる「夏みかん(夏橙)」は文旦の血を引く大果柑橘で、1700年頃に日本で発生した歴史の古い柑橘です。
甘夏は、昭和10年頃大分県の川野氏の園で、カラタチ台の普通夏橙として植栽された中から、減酸の早い品種として発見されたことから川野夏橙といわれていました。昭和25年に品種登録、昭和30年頃から愛媛県などで集団栽培が開始され、温州みかんに次ぐ柑橘でした。
昭和40年のグレープフルーツの輸入自由化によって大きな打撃を受け、生産・消費ともに減少の傾向にあります。
参照元:のま果樹園
夏みかんは江戸時代に山口県長門市仙崎大日比(青海島)に漂着した南方系の柑橘の種を育成したものが期限とされています。標準和名は「夏代々(ナツダイダイ)」ですが、「夏橙」や「夏柑」などとも呼ばれています。現在でも山口県をはじめ各地で栽培されてきましたが、現在ではほとんど甘夏(アマナツ)に取って代わっています。
甘夏ミカンにはいくつかの種類があるようですが、そのほとんどはカワノナツダイダイ(川野夏橙)だと言われています。カワノナツダイダイとは、古くからある夏ミカンの中から発生した変異種で、甘味系夏ミカンと呼ばれるものです。普通の夏ミカンよりも早く色付き、酸が早く抜けるのが特徴のためこう呼ばれるようになったようです。
参照元:旬の食材百科
「甘夏」は柑橘類について説明しているこの項目へ転送されています。
カワノナツダイダイ(川野夏橙)は、ミカン科ミカン属の柑橘類の一つ。1935年(昭和10年)大分県津久見市の果樹園で川野豊によって選抜・育成された、ナツミカンの枝変わり種である。甘夏橙、甘夏蜜柑(甘夏みかん)、甘夏柑、甘夏などとも呼ばれる。
ナツミカンに比べて減酸が早く糖度が高い。1950年(昭和25年)に品種登録された後に1955年(昭和30年)ごろより増殖が進められ、1965年(昭和40年)ごろからはナツミカンからの更新が進んだが、1971年(昭和46年)のグレープフルーツ輸入自由化以降生産量は減少傾向にある。2008年現在、出荷量は熊本県が首位、愛媛県が2位である。
冷蔵庫での保存は、苦味が出るため、禁物である。
「甘夏」は元々「夏みかん」だったようです。
夏みかんは1700年代(江戸時代)に、山口県長門市仙崎大日比(青海島)に漂着した南方系の柑橘の種を育成したものが起源であり、別名を「夏代々(ナツダイダイ)」や「夏橙」、「夏柑」と言います。
その後、夏みかんは1935年(昭和10年)に、大分県津久見市の川野豊氏の果樹園で変異種が発生し、その変異種が「甘夏(あまなつ)」になりました。別名を果樹園主の川野氏の名をとって「川野夏橙(カワノナツダイダイ)」と言い、ウィキペディアでは「甘夏」のページは存在せず、「カワノナツダイダイ」のページに転送されます。
甘夏は夏みかんより糖度が高く、1950年(昭和25年)に品種登録され、生産が拡大されていきましたが、1971年にグレープフルーツの輸入自由化を機に生産が減少しました。2008年は熊本県が生産量1位、愛媛県が2位とのことです。
自然栽培とは何か?
自然栽培とは農薬を使わず、肥料も使わない野菜の栽培方法。動物性の堆肥は使用しない。自分の畑で出た植物残渣を3年ほど寝かした植物性堆肥は育苗時に使用することもある。
野菜には「窒素」「リン酸」「カリウム」という三つの栄養素が必要だと言われ、慣行農法では多くの場合、化学的に生成した「化学肥料」を畑に撒いて野菜を育てる。
有機農法では化学肥料の代わりに牛や鶏などの家畜の糞尿、私たちの残飯や生ゴミを熟成発酵させたものや、外国から仕入れた油粕、魚粉などを配合したものを「有機肥料」として使う。
わたしたちが普段見慣れている野菜は農薬、化学肥料が使われている野菜です。そのような野菜の栽培方法を「慣行栽培」と言います。また、化学肥料の代わりに有機肥料を使う栽培方法を「有機栽培」と言います。有機栽培は無農薬のものもありますが、一部の認可されている農薬を使うことができます。必ずしも「無農薬」というわけではありません。
上記の慣行栽培、有機栽培に対し、自然栽培は農薬、肥料を使用せず、自然のチカラを借りて作物を育てる栽培方法です。有機栽培では「有機JASマーク」が知られている通り、明確な認可機関がありますが、自然栽培にはありません。したがって自然栽培かどうかは、自己申告制になっており、明確な定義はありません。
明確な自然栽培の定義はありませんが、その栽培方法を細分化すると、畑を耕すか?、除草を行うか?、作物はF1種か?それとも固定種か?、自然栽培を始めて何年経つのか?、以前のその土地に肥料や農薬を使用していたか?などがあげられます。
これらの栽培方法の違いは別の記事で公開していますので、興味のある方は以下のリンクをご覧になってください。
今回私が購入した甘夏(あまなつ)は自然栽培のものです。自然栽培の作物は、まだ一般的なスーパーでは目にすることがほとんどなく、自然食品店でもあまり見かけません。個人的にはもっと自然栽培の作物が手軽に手に入るようになってほしいです。
自然栽培「甘夏」の見た目、味について

甘夏をインターネットで画像検索すると、色がオレンジっぽいものが多く、外見もゴツゴツしていなくてツルンとした感じの画像が多いです。夏みかんのような感じですね。もしかしたら、夏みかんの画像も間違えて入っているのかもしれません。
しかしながら、わたしが購入した自然栽培の甘夏は、色はオレンジと言うより、レモン色にちかく、皮も若干ゴツゴツした感じで、ゆずのようです。わたしは甘夏について詳しく知らないので、これが本来の一般的な甘夏の姿なのか、自然栽培だからこのようなレモン色、ゴツゴツ感なのか分かりませんでした。
味の方ですが、自然栽培なので「自然味」あるいは「野性味」が強く、パサパサして酸っぱい感じを予想していたのですが、実際は正反対でした。果肉はとてもジューシーで果汁が溢れ出てくる感じです。酸っぱいどころか非常に甘かったです。これには驚きました。
甘夏の皮の塩漬けを作った
甘夏を食べ終わった後、皮も何かに利用したいと思いました。折角の自然栽培ものなので、そのように頭に浮かんだのだと思います。インターネットで「甘夏 皮」を検索すると、ほとんどがピールやジャムの甘い加工品でした。自然栽培を好む方は砂糖やそれに類似する糖類の摂取を抑えている人もいると思います。私もその一人です。
そこで、ピールやジャムではなく、独自のやり方で「塩漬け」に挑戦してみることにしました。
材料は以下の2点です
・甘夏の皮
・塩
私が使った「甘夏の皮」は、2玉分で200gでした。塩の分量はどれくらいが適量か?わからなかったのですが、毎年梅干しを作るとき、梅5kgに対して塩1kgを使っているので、それを参考にして甘夏の皮200gの2割分の重さが良いと思い、塩は40gにしました。
使用した塩は「心と体にしみる塩」です。この塩は必須ミネラルを含む微量のミネラルが豊富な自然天日海塩です。「心と体にしみる塩」については下記リンクをご参照ください。
また、一般的な精製塩は純度ほぼ100%の塩化ナトリウムであり、これは塩というよりは人工的に精製した化学物質です。精製塩の摂りすぎは高血圧を引き起こし、様々な生活習慣病につながる危険性があります。塩は天然塩、自然塩を選んだ方が良いと思います。精製塩の危険性については下記のリンクをご参照ください。
さて、話しが若干それてしまいましたが、甘夏の皮を一口サイズに切り分けた後、甘夏の皮200gと塩40グラムをジップロックの袋に入れて、しっかりとチャックを閉じます。液体が漏れ出てくる可能性があるので、できれば2重にした方が良いです。私は以下の商品を2重にして使いました。

ジップロック フリーザーバッグ Mサイズ 45枚入 ジッパー付き保存袋 冷凍・解凍用 (縦18.9cm×横17.7cm)
後は、甘夏の皮と塩を入れたジップロックの袋を2枚の板の間にはさみ、上に2リットルのペットボトル2本を置いて、圧力をかけ、3日から4日おけば完成です。
味の方は、「甘夏の皮」の酸味、苦み、爽やかさ、「自然塩」の塩辛さ、うまみがミックスされて非常に複雑な味で、スーッとした後味です。作りたてのときは塩辛さが強いですが日が経つとまろやかな味になります。私は汗をかいた後や気分転換したい時によく食べています。
今回購入した「自然栽培 甘夏」の購入先について
さて、最後になりますが、私が購入した「自然栽培 甘夏」は都内にある自然食品店、ナチュラルハーモニー(下馬店)です。関東圏内では有名な自然食品店なので、ご存知の方もいるかと思います。値段は2玉で380円(税込)でした。

・東京都世田谷区下馬6-15-11
・電話 03-3418-3518
・営業時間 11:00〜20:00 (土曜のみ 10:00〜20:00)
・定休日 日曜日
・facebook
※東急田園都市線 学芸大学駅より徒歩8分
自然栽培の関連記事
自然栽培の関連書籍